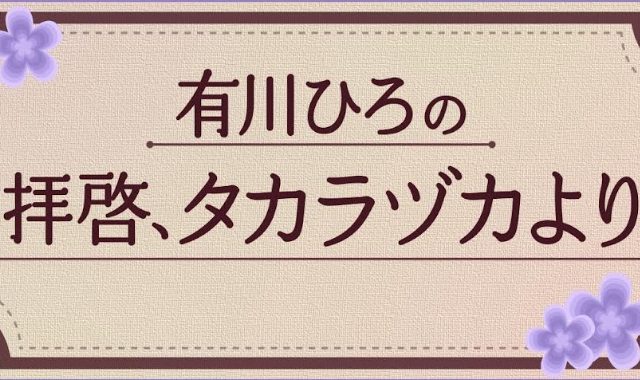当コラムはネタバレ全開につき読者各位におかれましてはご注意のほどよろしくお願い申し上げたし、とまずは勧告させて頂きつつ……
さて、これほどハードルの高いタイトルが他にあるだろうか。
そしてそびえ立つこのハードルを易々と飛び越えてくるトップスターがいる、雪組に。
その名は朝美絢、過去に幾度もその美貌でSNSを騒がせたタカラジェンヌだ。失礼ながら私は友人知人を宝塚沼におびき寄せるに当たってこの方の顔面を何度も利用させて頂きまして誠にありがとうございます。
美しすぎた男という副題は「なーんだ公式公認じゃん」という答え合わせでしかない。
その朝美絢演じるボー・ブランメルとは18世紀末のイギリス社交界に彗星のごとく現れたファッションリーダーである。彼の打ち立てた美学はダンディズムと呼ばれ、社交界の服飾の概念を根底から覆した。ボーとはフランス語で洒落者、その徹底した美意識に人々が捧げた通り名である。
だが、その物語は社交界の絢爛とは無縁の薄気味悪い場面から始まる。
冒頭、亡者のごとき異様な風貌で錯乱の歌と舞踊を繰り広げるのはウィリアム・ブランメル(諏訪さき)である。一体何が始まったのかとぎょっとする迫力で幼い息子ジョージ・ブランメル(愛陽みち)に呪詛を注ぎ込む。
壁の向こうには全てがある、何でも手に入る、俺は一度は壁を超えてあの社交界にいたのにたかが金の使い込みくらいで壁の外に追放された畜生どうしてくれる――下劣な他責性と自己弁護は、しかし鬼気迫る迫力に満ち満ちている。卑しいエゴを垂れ流す諏訪さきの怪演、無力にいたぶられる愛陽みちの熱演がこの作品のイメージボードだ。
かつての父と自分の様子を高い壁の上から冷ややかに見下ろすブランメル。その人生は亡者と化した父に歪められた。
ブランメルは父と幼い自分を置き去りにして壁の向こうへ歩き去る。父が手に入れられなかった全てを手に入れ、卑しい父を嘲笑ってやる――ブランメルを昏い情熱が駆り立てる。
さて、ブランメルが乗り込んだ社交界はといえば、旧態依然とした古臭いファッションがはびこり、野暮と悪趣味を佃煮にしたような有様になっていた。親父ウィリアムよ、本当にここで全てが手に入るのか? だいぶモッサリした畑やぞ?
皇太子殿下プリンス・オブ・ウェールズ(瀬央ゆりあ)も畑の惨状には薄々気づいている模様。その日プリンスはお気に入りの女優であり愛妾でもあるハリエット・ロビンソン(夢白あや)を伴い、かつての愛人デボンシァ公爵夫人(華純沙那)の夜会に訪れる。公爵夫人が話題の粋人ボー・ブランメルを夜会に招いたと聞いたからだ。
しかし元愛人の夜会に今の愛人を連れていくとはプリンスなかなかに人の心がない。女同士のバチバチも我関せずで昔の女の前でハリエットの美貌を自慢、王族の特異なパーソナリティが何気なく伝わってくるエピソードだ。公爵夫人の能面のような顔が恐いこと恐いこと。
そこにボー・ブランメルの登場である。古臭いファッションの紳士淑女を、スッキリと洒脱な衣装に身を包んだ美貌のブランメルは毒舌御免と切り捨てる。プリンスにすら媚びないその傲岸不遜な個性は逆にプリンスの心を鷲づかみ。美しいものと美しいものが踊るところを見たいとブランメルとハリエットのダンスをご所望になるが、実はブランメルとハリエットは若かりし頃の恋人同士であった……
この場面にはブランメルを支援する貴族の青年ピアポント(縣千)とその仲間たちも登場し、プリンスとブランメル、ハリエットと公爵夫人だけでなく、野次馬を決め込んでいるいけすかない青年グループの様子も見逃せない。彼らはブランメルが社交界の頂点へ上り詰めることができるかどうかを賭けている、それも遊び半分に。
この夜会でブランメルに惚れ込んだプリンスはファッションアドバイザーを兼ねた友人としてブランメルにお召しをかけ、ブランメルはもったいぶって仰せつかまつる。ハリエットは昔の男に今のパトロンの前をうろちょろされて気が気でない。
さて宮廷にブランメル旋風が吹き荒れる中、プリンスに(特にその放蕩と金遣いに)冷ややかな眼差しを向ける一派があった。英国議会のトーリー党議員たちである。党の精神的支柱はどうやら若手のジェンキンソン(華世京)、プリンスの享楽をお諫め申し上げねばと知恵を巡らす。目をつけたのは皇太子妃キャロライン(音彩唯)。
享楽三昧で閨に寄りつかぬプリンスに女のプライドも皇太子妃の矜持もバッキバキにへし折られ、国の未来のためにもお灸を据えてやらねばと青白い怒りに燃えている。女としても怒り心頭であろうにそれでもしかし国のためと考えられるところが非常に理知的な女性だ。終盤、お灸で丸焦げになったプリンスへの申し出は実に気高い。
宮廷にはブランメル旋風が吹き荒れるが、ブランメルの周辺はあまり平穏ではない。失脚の火種はそこかしこという中、かつての恋人ハリエットと焼けぼっくいに火がついて愛が再燃してしまう……
個人的には宮廷劇でありながら個人のエゴに振り切っているのが宝塚では珍しい作風に思えた。宝塚初心者マークの私にとって、宮廷を舞台にした宝塚作品は登場人物が何らかの大義を抱えていることが多いイメージだったが(それがミニマムなものであっても個人としての大義があるイメージだ。愛に生きるようなものも含めて)『ボー・ブランメル』は芯にあるのがあくまでブランメルのエゴである。そのエゴは破滅した父親から呪詛のように注ぎ込まれたものだが、呪詛であるからしてエゴのどこをどう引っくり返したとて大義は生まれ得ない。
父親のエゴに取り憑かれた子供がその支配を相克するために父親が手に入れられなかったものを手に入れることを欲する、どこまでも「個人的な」話であることが新鮮だった。
諏訪さきのグロテスクな父親の演技に息が苦しくなる人もいそうな作品だ。ブランメルの心象の中で父親はもはや化け物であり、ブランメルは化け物の呪詛を逃れたいその一心に無意識を支配されている。
このブランメルのエゴを周囲の人物が削ることで研ぎ澄まされていく作品のように思ったが、ブランメルとエゴを戦わせるポジションにいるのはキャラクターの配置的にプリンスとピアポントに限定されている印象だ。
そしてこの二人がまあ削る削る。
ピアポントは中の人が座談会で「親友です!」と自己申告していたが、こちら盛大なジョークと思われる。その爽やかなルックスに反して実にスノッブ、下衆の二文字がよく似合う。ブランメルという毛色の変わったオモチャを手に入れ、社交界の頂点を目指すというこの大それた平民を遊び尽くす気満々。ブランメルの野望に資金まで出してやる。
ピアポントはいつもにこやかにブランメルを焚きつけるが、言葉や振舞いにはたっぷり毒が含まれている。友人ぶっているがピアポントらは決してブランメルを対等には見ていない。またそれを折に触れブランメルに思い知らせる。何気なくにじむ底意地の悪さは悪意ですらなく、邪悪な好奇心だ。
おだて上げたらこいつは一体どこまで舞い上がるのか、舞い上がった後にどうなるのか。地べたに叩きつけられて粉々になってもそれはそれ、壊れたらまた次のを探すさ――冒頭からのピアポントの表情を追っていると悪気ない残酷さがほの見えて興味深い。人間の度しがたさを見せつけられているようでもある。
ブランメルが何をしても無責任に面白がっているばかりだったピアポントが、一度だけ真顔で忠告する。ハリエットはやめろ、プリンスにバレたらどうなると思ってる。
ブランメルはバレるはずがないと高を括る。「君がバラさない限りはね」――思うにピアポントはこのときブランメルから「下りる」ことを決めたのではないか。
対等になどなれるはずもない平民にこの俺が本気で忠告してやったのに、という怒りは高慢な貴族としてあり得る心の動きだ。少なくとも積極的にブランメルの破滅を回避してやる行動はこれ以降取らなかったのではないか。
忠告したのはブランメルをけっこう気に入っていたのかも? しかしブランメルが忠告を聞いていたとしても自分の忠告を聞いた時点で予測不能なオモチャとしての価値は半減、結局は飽きて放り出したかもしれない。
何不自由ない裕福な貴族の青年は、一体何を欲して生きているのか。ただ退屈をしのぐためだけに人生を費やしているようにも見える。さよならだけが人生だなんて詩があったが、貴族たちにとっては退屈だけが人生なのかもしれない。
壁の向こうには全てがある、何でも手に入ると妖怪親父は言ったがしかし、何でも手に入るということは何も持っていないのと同じことなのかもしれない。努力なしに手に入るものは魅力を失う。
裕福な貴族の青年が熱く血をたぎらせる術はこの時代の社交界にはない。ピアポントはもしかするとブランメルに退屈な世界の破壊者となることを期待していたのか。
終盤、失脚したブランメルを追い詰めるピアポントはひどくサディスティックで、それはブランメルが退屈の破壊に失敗したことへの懲罰のようにも思える。
あるいは、自分が一度も血をたぎらせることなく生きていくことへの苛立ちなのか。
そしてピアポント以上に何もかも持っている、持っていないものが何もないプリンスである。人の心がないと前述したが、それも当然。何故ならプリンスは誰からも人間として扱われていないからだ。人間として扱われたことがない者がどうして人間のような振る舞いができよう。
人々はプリンスにおもねり、おだて、あがめ奉る。社交界はプリンスの歓心を買うゲーム場で、プリンスは上手に振ればありとあらゆる富と名声を降らせてくれる打ち出の小槌だ。プリンスを生身の人間として扱う者は誰もおらず、プリンスは神棚に祀り上げられている。イギリスに神棚があるかどうかは知らん。打ち出の小槌も知らん。
プリンスは祀り上げられた神棚に疑問を抱かず、ちやほやされて生涯ご機嫌でいられる愚鈍な知性の持ち主だったら幸せだった。悲劇はプリンスが聡明であったことだ。
プリンスの知性は享楽三昧の諫言にまかり出た議員たちをすかさず理屈でやり込める機転にも現れている。
おそらくプリンスは知っている、自分が貴人であるために逆に人間として扱われていないことを。ゴテゴテのデコラティブな衣装が悪趣味なことも。だが別に嫌な思いをしたいわけではないので諫言する人々は遠ざけ、「まあこんなもんか」と程々のぬるま湯に浸かっている。
そんなプリンスを服がダサいと一刀両断したブランメルの痛快さよ。
「やっぱりィ!? やっぱダサいと思ってたんだよ俺もさぁ!」――という感じだろうか、話の分かる相手に巡り会ったときの高揚は王族といえども同じ、いや歯に衣着せぬ相手と巡り会ったことがないだけに余計に鮮烈だったろう。
プリンスがブランメルの誂えた服に着替えたとき、ブランメルが眉をひそめて職人にささやく。
「カツラは何とかならないのか」
当時、紳士淑女の身だしなみであったカツラがブランメルスタイルに合わず台無し。
だが、ごちゃごちゃ揉めているブランメルたちを尻目に、プリンスは姿見の前で自らカツラを取り払う。ブランメルに劣らず涼やかな美貌が現れるこのシーンは鮮烈だった。
このスタイルにこの髪は合わないと判断できるセンスと知性があり、またカツラという当時の固定観念を躊躇なく脱ぎ捨てられる柔軟性も持ち合わせていることをカツラを取り去る一動作、それも背中で表現する瀬央ゆりあの演技力よ。
ブランメルはやるなとプリンスにちょっと一目置き、二人の交流が始まる。
裏切りの影に女あり、二人の蜜月が壊れたきっかけはブランメルとハリエットの愛の再燃である。しかしこれを裏切りと呼ぶのもむごい。
父親の呪縛に囚われて失った恋だ、社交界でのし上がることで呪縛を振り払ったと信じた刹那に失った恋人と出会ってしまったことが不幸だ。父親に奪われたものを取り戻せると錯覚してのめり込む恋はさぞかし甘やかであったろう。
しかし二人が裏切っているのはプリンスだ。
先に耐えられなくなったのはハリエットだ、ハリエットは社交界を生きるには純粋すぎた。女優として上流社会に紛れ込んでしまった普通の女の悲劇が痛ましい。
ハリエットに袋小路の現実を突きつけられ、ブランメルは自分が何を質に入れて栄光と恋を手に入れていたのかを知る。
秘めた恋は暴かれ、手に入れた全てを奪われるターンが来た。小金を横領して追放された父親のように。
投げやりになっていたブランメルにプリンスの使者が来る。ピアポントだ。
呼び出された夜会にはハリエットも来る。それを聞いて濁っていたブランメルの目に火が入る。
デボンシァ公爵夫人の夜会でプリンスは冷ややかに二人の公開処刑を始める。
ハリエットも俎上に乗せられてはいるが、プリンスが切り刻もうとしているのは明らかにブランメルだ。ブランメルを愛したことはないといじらしい嘘を吐くハリエットをプリンスは一顧だにしない。余が信じるのはブランメルの言葉だけだ――
その宣告はブランメルにハリエットと同じことを言えという命令だ。ハリエットを愛したことなどないとプリンスはブランメルから聞きたいのだ。
ハリエットはプリンスにとって気の向くままに取り替えていく愛妾の一人だ。ハリエットの番は終わった、それ以上でも以下でもない。
ブランメルには恐らく生まれて初めて皇太子の友人という名誉を与えた。にも拘らずブランメルはプリンスの女を盗んだ。自分との友情よりもありふれた恋を選んだ、プリンスはそれが許せない。
手に入らないものは何もない、しかし欲するものは何も手に入らない。そのジレンマへの怒りが裏切りという口実を見つけてブランメルに襲いかかる。
ブランメルよ、余を選べ。さもなくばお前は全てを失う――
友情とはそのように強いるものではないとプリンスは知らない。
ブランメルは、――手に入れたものを全て地べたに投げ捨て、自ら踏みつけた。
惜しむ気配すらなく踏みつけられたプリンスがひとすじ涙を流す。その涙は彼が初めて生身の人間になった証であろう、苦くはあるが。
自分の思いどおりにならないものがこの世にあるということを彼は初めて知ったのか。それほどまでに欲したブランメルは、プリンスにとって一種の愛であったのか。
その後ブランメルは、自分の失脚を仕組んだジェンキンソンにハリエットの保護を頼む。最後にブランメルがハリエットを託すに値すると信用したのが自分を陥れた政治家だったことは皮肉だが、ジェンキンソンは政治家として公正ではあった。
そしてブランメルは劇場を訪れた皇太子夫妻の前に正装で現れる。
ブランメルの慇懃な礼を皇太子夫妻は昂然と無視して立ち去る。――もはや終わったこと。
そしてブランメルはハリエットの楽屋に真っ赤な薔薇の花束を置いて劇場を去る――
イギリスではどうか知らない、だが最後の装束の色は日本では弔いの色でもある。
灰色の濁った装束に包まれていた亡者の父とは対照的な清々しさだ。
壁の向こうで手に入れたもの何もかも奪われるのではなくみな投げ捨てて。
彼は質に入れていた自分の魂を取り戻した。
最後にシルクハットを静かに投げ捨て、ブランメルは我々に背を向けて歩き去る。いずこと知れぬ光の中へ。
その後ろ姿は眩しく輝いて、――もう我々には何も見えない。
私は裸で母の胎を出た。裸でそこに戻ろう――という聖書の一節をふと思い出した。