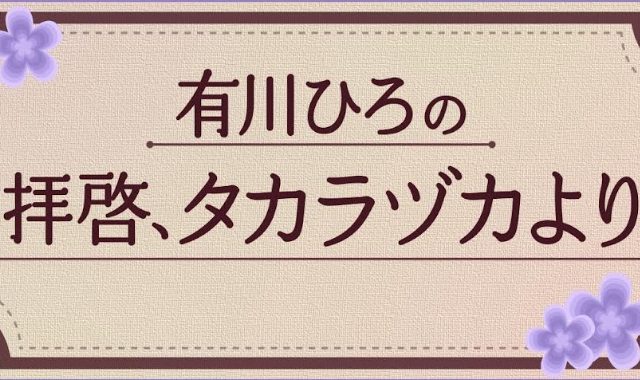観たヨーシリーズ第二弾。というわけで雪組『パリのアメリカ人』である。
物語は第二次世界大戦終戦後のパリだ。主人公は元アメリカ軍人にして絵描きのジェリー(朝美絢)。終戦して祖国に引き揚げるはずが、混乱するパリの街でおばあさんを助けた心優しいパリジェンヌに一目惚れして帰国を中止。パリで画家として生きる道を模索しつつ一目惚れの彼女との再会を夢見る。……なかなか後先考えない、いかにもアメリカ人らしい陽気さと無鉄砲さに溢れた青年である。
ジェリーは芸術に理解のあるカフェの主人に下宿を許され、そこでショーマン志望のアンリ(瀬央ゆりあ)と作曲家志望のピアニスト・アダム(縣千)に出会う。アンリはパリの繊維会社の御曹司、アダムはユダヤ系アメリカ人の元アメリカ軍人。アダムは戦争で負傷して右脚が不自由になっているが、指を軽やかに鍵盤の上で踊らせ、アンリは彼の曲で歌い踊る。二人が目指すのはNYのラジオシティホール。
ジェリーも画家として活動しながら彼らとの友情を育む。
そんなある日、ジェリーはバレエスタジオのオーディションをスケッチしに行く。スタジオでピアノの演奏係を勤めるアダムが誘ってくれたのだ。
そしてそのオーディションで、ジェリーは一目惚れしたパリジェンヌ・リズ(音彩唯)との再会を果たす……! のだが、アダムもリズに恋してしまい、恋愛レースは混戦模様。
そして二人は知らぬことながら、実はアンリがプロポーズしようとしている女性もリズだった。
固い友情で結ばれた三人がたった一人の女性をそれぞれ愛してしまう、その顛末や如何に。
私は『パリのアメリカ人』という物語に触れるのは初めてだったが、あらすじから可愛くも真摯な恋物語を想像していたら、真摯だし恋物語なのだが、それ以上に戦争の傷跡から立ち直ろうとする人々のイメージが強い作品だった。
戦争で皆それぞれに傷ついている、しかしそれでも立ち上がって光へ向かおう――という趣旨の台詞を残して舞台の袖へ去っていく終盤のアダムは、戦争だけでなく世のままならなさを味わったことがある全ての人々に歩き出す勇気を見せている。
この台詞を担ったのが足の悪いアダムであったことは偶然ではないだろう。動かぬ足を引きずって、それでも人は光を目指して歩いて行かねばならない。拙い足の運びでも、一歩一歩。
アダムは杖を嫌い、動かぬ足を無造作に引きずって歩く。動かぬ足を時にもどかしく手で強引に動かしながら、腱が効かない代わりに骨の角度で体重を支えながら。
そのぎこちなくも力強い動きは、アダムの不自由さより生きる意志を感じさせる。
観客はその動きに「そうあれかし」と自分のままならなさを重ねるだろう。
とは言いつつも、やはり気になるのは恋の行く末である。
真っ先に脱落するのはアダムである。リズと出会ったときは、オーディションに遅刻して帰らされそうになったリズをピアノの片手間にちょいちょい招き寄せ、「後ろのほうにまぎれちまえば分かりゃしない」と入れてあげるという「惚れてまうやろ」仕草をぶちかましてくれるのだが、リズを意識したら途端にコミュ障ポンコツになってしまう。
ジェリーとアンリがリズを巡って大喧嘩するときも、ジェリーをぶん殴ったアンリを「おしまいだアンリ。……アンリ」と低い声で制して宥めるところなどはちゃめちゃに男っぽくてカッコいいのだが、いかんせん彼のカッコよさは意識してない他人枠の女子か男友だちにしか発揮されないらしい。不憫。
というわけでアダムは一人空回っているだけなので、真の恋敵はジェリーとアンリである。
ジェリーは底抜けの陽気さでぐいぐいリズに迫っていく。職場に押しかけ勝手にリズの退職を宣言し、迷惑がるリズを振り回す。甚だ押しが強く甚だアプローチの圧が強い。これは朝美〈顔がいい〉絢でなければ事案である。おまわりさんこの人です!
もはや顔がいいだけでは許されないレベルの暴挙だが、そこは役者・朝美絢の演技力の賜物。憎めない不思議な愛嬌があり、リズも怒りながらつい笑ってしまう。
それは観客も同じで、「何だこいつは」と思いつつ、いつのまにかジェリーの恋を応援してしまう。
リズは何故かいつも思い詰めた悲壮な顔をしている。しかし、そんな抑圧的なリズに笑顔をこぼれさせるのはジェリーの底抜けの明るさと強引なアプローチ。最初はちょっと怒りながら、困惑しながら、しかしいつのまにか弾けるように笑っている自分に気づいてリズは戸惑う。戸惑うたびに笑顔は引っ込み、しかしくじけないジェリーのおふざけでまた笑顔がこみ上げ――
「リズっていい名前だね、でもちょっと寂しそうだ。ニックネームをつけよう」
余計なお世話とリズは怒るが、ジェリーはかまわずリズに「ライザ」というニックネームをつける。ライザでいるときは楽しくなっていい、笑っていいと強引な決め打ちとともに。
リズは無視して帰るかと思いきや、ジェリーのペースに巻き込まれてしまう。
結局ジェリーの言ったとおり、毎日待ち合わせの橋で絵のモデルになってしまう。
迷惑がりながら、「ただの友だちだからね」と釘を刺しながら、屈託のない笑顔はジェリーと一緒にいるときだけ――
ジェリーはそんなリズにずっと「ライザ、笑って」と歌いかける。
君が笑ってくれることが僕の一番の願い。
一方、アンリはリズにプロポーズするべくラブレターに四苦八苦。
リズは昔からアンリの家で世話になっており、アンリの両親ボウレル夫妻も息子とリズの結婚を望んでいる。由緒ある家柄の御曹司がその歳まで結婚しないのはおかしい、お前は義務を果たさねばならない、リズなら花嫁として申し分ない――両親の圧に押されるようにアンリは求婚に取り組む。まるで試験に挑む生徒のように。
パンフレットによると、アンリはある秘密を抱えている。その秘密は劇中でアンリの母によりやや乱暴に開示される。
実はアンリの愛する対象は女性ではないのではないか。
当時、同性愛は国によっては違法とされた。ナチス占領下のフランスでは同性愛者が強制収容所へ送られた。同性愛が全くオープンでなく、罪にさえなる時代の話である。
アンリは母親からの疑惑を否定するのではなく、「それは言わないで」と押しとどめる。解釈の余地は広い。だが、ところどころにそれを匂わせる描写はある。
一方で、アンリのリズへの愛情も嘘とは思えない。リズを巡ってジェリーに殴りかかったりもする。
解釈は人それぞれなので、以下は私の勝手な解釈だ。
アンリは母親の疑惑を肯定しないが否定もしない。そしてアンリとアダムの喧嘩を仲裁しようとして「お嬢ちゃんたち」と語りかけるジェリーに、「僕はお嬢ちゃんじゃない!」と激昂する一面も見せる。
自分の愛する対象がどちらなのか、アンリは自分でも計りかねているのではないか――と私は思った。だが、「こうあるべき」という社会規範は現代より厳然とあるし、両親もそう望んでいる。
自分が同性愛者であるという明確な自覚はない。だが、同性愛者でないという自信もない。
だが、リズのことは愛している。少なくとも、リズとなら結婚できると考えている。既に家族のような大切なリズだから。
そして恐らく、リズじゃないなら無理だとも思っているのではないか。だからこそ、リズへの求婚にあれほど怯えていたのではないだろうか――
リズに拒まれたら、他の「女性」との結婚は到底考えられない。それは彼の中で決めかねている曖昧な境界を、母からの疑惑どおり「結婚できない=女性を愛せない」側へ確定させてしまう。
「言いたくないことは言わなくていい。誰にだって隠しておきたいことくらいある」
折に触れジェリーが言うこの主義は、観客の中でアンリにも響いている。
アンリの自認はとても繊細だ。自分でも判断できないほどに。ジェリーとアダム、二人の前で母親からの疑惑を打ち明けようとしたのは、もしかすると二人に助けを求めていたのかもしれない。
もっとも同性愛がオープンでない時代のことなので、二人とも悪気なく話をはぐらかしてしまう。
もしこのときはぐらかされていなかったら――というのは、あくまでifの物語である。
劇中でのアンリはリズとの婚約の道を突き進む。
ライザ笑ってと歌いかけるジェリーに対して、アンリは「リズ教えて」と苦悩している。
教えて、僕らのあるべき姿を。
ボウレル家のパーティーで二人の婚約を知ったジェリー(とアダム)は荒れた。元よりレースをコースアウトしていたアダムはぐだぐだ落ち込むだけだが、ジェリーはそうは行かない。
パーティー会場を逃げ出したリズを追いかけて問い詰める。
「俺の目を見てアンリを愛していると言ってくれ」
そう言ってくれたら諦める覚悟が俺にはあるという男気だ。
リズは言えなかった。代わりに――
「陽気なアメリカ人と恋をするなんて贅沢はわたしには許されていないの」
こんなことってあるか。
こんなの、あなたが好きと叫んでいるのと一緒じゃないか。
ジェリーを恋するのは許されない贅沢。こんな血を吐くような告白があるか。
こんなの、ジェリーだって止まれるわけがない。
どうしてと食い下がるジェリーにリズは言う。――わたしにはボウレル家の人々を尊重する義務がある。
愛は義務じゃない、とジェリーは吠えるが届かない。
実はリズはユダヤ人で、戦争中はボウレル家に匿われていた。両親は戦争中に逮捕され、生死は不明。だが、戦後も戻ってこないことで察せられる。
リズはボウレル家の恩義に報いるためにアンリとの結婚を決めた。ここにも戦争の忘れ得ぬ傷跡がある。
事情を知ったジェリーは身を引く決心をする。ジェリーもまた、戦争で忘れ得ぬ傷跡を負った人であった。
戦後のフランスで、誰も戦争の記憶から逃れられない。
結果的に、リズはバレエのデビューを果たしたラストでアンリに送り出されるようにジェリーの元へ戻るのだが、そこに至るまでの間にアンリの自認について思いを馳せられる場面がある。
アンリの夢であったショーデビューを、知り合いのカフェでささやかに叶える夜である。緊張してボロボロになっていたアンリに、ピアノを弾きながらアダムが怒鳴る。
「夢を叶えるんだろ!(あんなに思い描いていた)ラジオシティのことを思い出せ、相棒!」
ショーはイメージの中でラジオシティに飛ぶ。アンリは堂々と階段を下りて歌い踊る。
そんな中、アダムがお揃いのタキシードで乱入する。
夢の中なのでアダムの足は自由に動く。アンリは自由に動けるアダムとショーを踊り、ふと我に返ると現実のショーも大成功を収めていた。
そして、リズのバレエデビューでもこの展開をなぞるような演出がある。
リズはイメージの中でジェリーと踊る。
自分が一番自由でいられる人と。
バレエの発表会は大成功を収めて、万雷の拍手で終わる。
リズが思い浮かべたのはジェリーだった。
アンリが思い浮かべたのはアダムだった。
リズとジェリーとは違って恋や愛ではないかもしれない。だが、自分が一番自由でいられる人としてアンリが思い浮かべたのは、リズではなく夢の相棒たるアダムだった。
それだけは事実で、――そして、それだけでいいのだろう。
アンリの夢の中で、アダムの足は自由に動いた。それは僕と共にそうあれかしという願いか。
ジェリーが何度も言ったように、「言いたくないことは言わなくていい」。言いたくないことの中には、分からないから言いたくないことも含まれるだろう。
言葉に出して決めてしまうと、曖昧なあわいは消えてしまう。曖昧さの中にしか生きられない柔らかな心がきっとある。ジェリーはきっとそのことを知っている。
誰よりも奔放で自由気ままなジェリーは、実は誰よりも賢者で、誰よりも優しい。その優しさがジェリーに関わる全ての人々を幸せに導く。
これまでも、そしてこれからも。
結ばれたジェリーとリズを橋の上に残して、アダムとアンリが去る。
階段を下りにくそうなアダムに、アンリが自分の肩を掴めと差し出す。
冒頭、動かない足を拒絶するかのように杖を嫌っていたアダムは、素直にアンリの肩を掴んで下りる。
二人はいつかラジオシティホールに立つのだろう。
そして、その客席にはジェリーとリズが招待されているに違いない。
プロフィール
有川ひろ 高知県生まれ。2004年『塩の街 wish on my precious』で「電撃小説大賞」を受賞しデビュー。同作と『空の中』『海の底』の「自衛隊三部作」、「図書館戦争シリーズ」、「三匹のおっさん」シリーズをはじめ、『阪急電車』『植物図鑑』『県庁おもてなし課』『空飛ぶ広報室』『旅猫リポート』など著書多数。2019年に「有川浩」より「有川ひろ」に改名。最新作『クロエとオオエ』は神戸のジュエリーショップがモデル 宝塚歌劇の大ファンでも知られる。